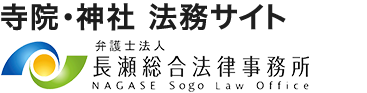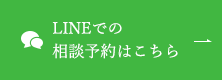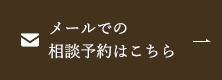2025/09/07 コラム
墓地経営許可の取得|墓地、埋葬等に関する法律に基づく申請実務と法的留意点
はじめに
寺院にとって、墓地の経営と管理は、古くから続く重要な役割の一つです。檀信徒の方々が安らかに眠る場所を提供し、その祭祀を永続的に執り行うことは、寺院の活動の根幹であり、安定した運営の基盤ともなっています。
しかし、墓地は誰でも、どこにでも自由に作れるわけではありません。お墓が持つ国民の宗教的感情や、公衆衛生への配慮から、「墓地、埋葬等に関する法律」(通称:墓埋法)に基づき、都道府県知事(または権限移譲を受けた市町村長)から「経営許可」を得ることが法律で厳しく義務付けられています。
この経営許可の審査は、「永続性」と「非営利性」という観点から厳格であり、周到な事業計画と、地域住民への丁寧な説明、そして複雑な行政手続きをクリアしなければなりません。安易な見込みで計画を進めてしまうと、許可が下りずに多大な時間と費用が無駄になってしまうリスクも潜んでいます。
この記事では、宗教法人が新たに墓地を経営するために不可欠な「墓地経営許可」に焦点を当て、法律上の許可要件、申請手続きの具体的な流れ、そして申請にあたって特に注意すべき点について、Q&Aを交えながら解説します。
Q&A
Q1. 寺院で所有している山林の一部を切り開いて、檀家さん向けの新しい墓地を作りたいと考えています。どのような手続きが必要になりますか?
新たに墓地を経営するためには、「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)に基づき、都道府県知事(または市や区の長)の経営許可を得る必要があります。手続きの最初のステップは、計画の初期段階で、自治体の担当部署(保健所や環境衛生課など)へ「事前相談」に行くことです。そこで計画の概要を説明し、許可の見込みや、その自治体独自の条例・指導要綱で定められた基準(周辺住宅との距離など)を確認します。その後、周辺住民への説明会を開いて同意を取り付け、都市計画法など、他の法律に関する部署とも協議を重ねた上で、ようやく正式な許可申請に至ります。数年単位の時間がかかる、計画的な準備が必要な手続きです。
Q2. 墓地経営の許可は、誰でも申請できるのでしょうか?私たちのような宗教法人が申請する場合、何か有利な点はありますか?
墓地経営の主体は、その永続性と非営利性が問われるため、誰でもなれるわけではありません。多くの自治体の条例では、経営主体は原則として「地方公共団体」に限定されています。ただし、例外として、古くから祭祀を主宰してきた実績があり、非営利性と永続性が担保されやすいという理由から、「宗教法人」や「公益法人」には、特例的に経営が認められています。株式会社などの営利企業が、単独で墓地経営の許可を得ることは原則としてできません。その意味で、宗教法人であることは、墓地経営許可を得るための出発点として、法律上、有利な立場にあるといえます。しかし、有利な立場とはいえ、財政基盤の安定性などは厳しく審査されます。
Q3. 墓地経営の許可申請は、どれくらいの時間がかかりますか?また、申請すれば必ず許可されるというものではないのでしょうか?
許可申請にかかる期間は、計画の内容や自治体によって大きく異なりますが、事前相談から許可証の交付まで、少なくとも1年、長い場合は2~3年以上かかることも珍しくありません。特に、周辺住民の方々への説明と合意形成に時間がかかるケースが多く見られます。そして、申請すれば必ず許可されるという保証は全くありません。自治体が定める条例の基準を一つでも満たしていなかったり、住民の強い反対があったり、事業計画の実現性に疑問があると判断されたりした場合には、不許可となる可能性も十分にあります。だからこそ、計画の初期段階での入念な調査と、専門家を交えた周到な準備が、計画の成否を分けることになります。
解説
1. 墓地経営の許可制度:墓埋法と地方条例
墓地経営許可制度の目的は、墓埋法第1条に「国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われること」と定められています。しかし、法律本体(墓埋法)は許可制度の枠組みを定めているに過ぎず、許可の具体的な基準はほとんど書かれていません。
実際に許可審査で適用される詳細な基準、例えば「墓地の設置場所」や「施設の構造」に関する要件は、各地方公共団体が定める条例や指導要綱に委ねられています。したがって、計画に着手する前に、まず計画地の自治体が定めるこれらのルールを正確に把握し、遵守することが何よりも重要です。
なお、墓埋法の施行規則は随時改正されており、最新の情報を確認することも大切です。
2. 墓地経営の「許可基準」― 3つの柱
一般的に、条例で定められる許可基準は、大きく分けて以下の3つの柱で構成されています。
- 経営主体の要件(永続性・非営利性)
原則は地方公共団体ですが、宗教法人や公益法人に例外的に認められます。ただし、宗教法人であれば無条件ではなく、宗教活動の実績や安定した財政基盤などが求められます。 - 設置場所の要件(立地基準)
公衆衛生や周辺環境への配慮から、厳しい制限があります。- 周辺施設との距離
学校、病院、住宅地などから、一定の距離(多くの条例で100メートル以上など)を離すことが求められます。 - 法令上の制限
「都市計画法」上の市街化調整区域や、「農地法」上の農地など、他の法律で開発が制限されている土地では、設置は困難です。
- 周辺施設との距離
- 施設の要件(構造設備基準)
墓地の周囲に塀やフェンスを設置することや、駐車場、給水設備、トイレなどの設置が義務付けられることが一般的です。
3. 墓地経営許可の申請手続きフロー ― 戦略的アプローチの重要性
許可取得までの道のりは長く、計画的かつ戦略的に進める必要があります。特に重要なのは、公式な申請書を提出する前の「事前準備段階」です。
【フェーズ1】計画の成否を分ける最重要の事前準備段階
- ステップ①:行政との「事前相談」
構想が固まったら、図面作成や測量といった費用をかける前に、まずは計画の概要を持って自治体の担当窓口へ「事前相談」に行きます。このプロセスは単なる手続きの確認ではありません。行政側が計画の実現可能性を探り、特に地域社会とのコンフリクト発生のリスクを評価する場です。ここで得られる行政の感触が、計画を続行すべきか否かの重要な判断材料となります。 - ステップ②:周辺住民・利害関係者への説明と同意形成
多くの自治体では、近隣住民への説明会開催とその同意を、申請の事実上の前提条件としています。このプロセスが、許可申請全体で最も困難で時間を要する段階です。墓地建設計画は地域からの反対を受けやすいため、計画の初期段階から誠意ある丁寧な説明を繰り返し、理解と協力を得ていく姿勢が不可欠です。
【フェーズ2】公式な手続き段階
- ステップ③:関係各課との事前協議
都市計画課、農業委員会、林務担当課など、複数の行政部署との事前協議を並行して進める必要があります。 - ステップ④:許可申請書の正式提出
上記の事前調整がすべて完了して初めて、正式な許可申請書を提出します。申請書には、法人に関する書類、意思決定の議事録、財産・事業計画に関する書類、土地・図面に関する書類、住民の同意書など、様々な書類を添付する必要があります。 - ステップ⑤:行政による審査・現地調査・審議会
申請書が受理されると、書類審査、現地調査が行われます。また、多くの場合、専門家で構成される「墓地経営審議会」などに諮問され、計画の妥当性が審議されます。 - ステップ⑥:許可証の交付と工事の開始
すべての審査をクリアして、ようやく許可証が交付されます。この許可証を得て初めて、墓地の造成工事に着手できます。工事完了後、再度行政の完了検査を受け、これに合格して、墓地としての使用を開始することができます。
弁護士に相談するメリット
墓地経営許可申請は、単なる書類仕事ではなく、行政や地域社会との交渉・調整を伴う一大プロジェクトです。
- 計画の実現可能性の初期診断
- 行政協議・折衝の円滑化
- 質の高い申請書類の作成支援
- 住民合意形成プロセスの戦略的サポート
- プロジェクト全体の工程管理
まとめ
宗教法人が新たに墓地を経営することは、社会的な要請に応える意義深い事業ですが、そのためには、墓埋法と各自治体の条例に基づく、厳格な「経営許可」を取得しなければなりません。その道のりは、「事前相談」に始まり、「住民の同意取り付け」へと続く、長く険しいものです。特に、計画の初期段階における自治体との「事前相談」と、地域社会との信頼関係を築く「住民の同意」が、計画の成否を分ける二大関門といえるでしょう。
墓地の新規開設を検討される際には、計画の初期段階から弁護士にご相談ください。専門家と二人三脚で、法的なリスクを一つひとつクリアしながら手続きを進めることが、事業を成功に導くための道筋となります。
長瀬総合のYouTubeチャンネルのご案内
法律に関する動画をYouTubeで配信中!
ご興味のある方は、ぜひご視聴・チャンネル登録をご検討ください。