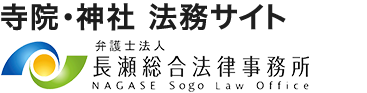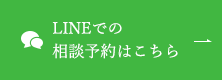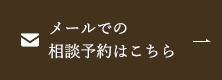2025/09/05 コラム
宗教法人の「規則」詳解|法人運営の憲法を定める作成・変更手続きと法的要件
はじめに
すべての宗教法人には、その組織運営の根本的なルールを定めた「規則」が存在します。この規則は、単なる内部の申し合わせ事項ではありません。宗教法人法に基づき、法人の設立時に必ず作成され、所轄庁の認証を受ける、いわば法人の“憲法”ともいうべき最も重要な規程です。
この規則には、法人の目的や名称といった基本情報から、代表役員・責任役員といった役員の選任・解任の方法、責任役員会の運営、財産の管理・処分に関する手続き、さらには法人の解散に至るまで、法人運営のあらゆる側面に関するルールが定められています。寺院の運営は、この規則に則って行われなければなりません。
しかし、法人設立から何十年も経過し、当時のままの規則で運営されている寺院も少なくありません。社会情勢の変化や、寺院の活動実態との間に乖離が生じ、いざという時に規則が機能しない、あるいは、近年の法改正が反映されていないために、コンプライアンス上のリスクを抱えているケースも見受けられます。
この記事では、寺院運営の根幹をなす「規則」に焦点を当て、その法的な役割、法律で必ず記載しなければならない事項(必要的記載事項)、そして規則を作成・変更する際の具体的な手続きについて、Q&Aを交えながら解説します。
Q&A
Q1. 寺院の「規則」とは、具体的にどのような役割を持つものなのでしょうか?なぜそれほど重要なのでしょうか?
宗教法人の「規則」は、株式会社でいう「定款」に相当する、法人運営の全ての基本となるルールブックです。その役割は大きく3つあります。
- 法人運営の安定化
住職や役員の交代があっても、法人運営のやり方が大きく変わることなく、ルールに基づいた客観的で安定した運営を可能にします。属人的な運営から脱却し、組織としての永続性を担保します。 - 内部紛争の予防
役員の選任・解任の方法や、不動産処分の手続きなど、特にもめ事になりやすい事項について、あらかじめ明確なルールを定めておくことで、将来起こりうる内部の対立や紛争を未然に防ぐことができます。 - 法人の自主性・自律性の担保
法律の基本的な枠組みの中で、各寺院がその歴史的背景や伝統、活動の実情に合わせて、独自の運営ルールを定めることができます。これは、宗教法人の自主性と自律性を尊重するという、宗教法人法の精神の表れでもあります。
Q2. 私たちの寺院の規則は、法人設立時から一度も見直しておらず、現在の運営実態と合わない部分が出てきています。規則を変更するには、どのような手続きが必要ですか?
規則を変更するには、大きく分けて ① 内部での変更決議 と、 ② 所轄庁への認証申請 という2つのステップが必要です。
まず、①については、ご自身の寺院の規則の中に「規則の変更に関する定め」という条項があるはずです。その条項に定められた手続き(例:「責任役員会の議決を経る」「責任役員の定数の3分の2以上の多数による議決を要する」など)に従って、規則の変更案を正式に議決する必要があります。
次に、内部で変更を決議したら、②所轄庁(都道府県や文化庁)への認証申請を行います。「規則変更認証申請書」に、変更議事録などを添付して申請します。所轄庁が審査し、内容や手続きに問題がなければ「認証」され、認証書が交付されます。この認証によってはじめて、規則変更の効力が生じます。所轄庁の認証なしに、内部だけで規則を変更しても法的には無効ですので、ご注意ください。
Q3. これから新しく宗教法人を設立しようと考えています。規則には、必ず記載しなければならないことがあると聞きましたが、それは何ですか?
はい、その通りです。宗教法人法第12条第1項には、規則に必ず記載しなければならない事項として13項目が定められています。これを「必要的記載事項」といい、一つでも欠けていると、規則として認証されず、法人を設立することができません。具体的には、「①目的」「②名称」「③事務所の所在地」といった基本的な事項のほか、「⑤役員の定数や任期、選任方法など」「⑧基本財産や宝物の管理・処分方法」「⑨規則の変更手続き」「⑩解散に関する事項」「⑪公告の方法」など、法人の組織、財産、運営に関する根幹的なルールが含まれます。
解説
1. 宗教法人の「規則」とは?法人運営の根本原則
宗教法人の規則は、その法人が法人として存在する限り、規範として機能します。役員も信者も、この規則に拘束され、規則に従って行動することが求められます。特に、寺院運営でトラブルが生じた際には、この規則の規定がすべての判断の基準となります。例えば、「代表役員のA氏を解任したい」と考えたとき、感情的に「A氏は代表役員にふさわしくない」と主張しても解任はできません。規則に定められた解任事由に該当するか、そして、規則に定められた解任手続きを踏んでいるか、という点が法的に問われるのです。
2. 規則の必要的記載事項(宗教法人法第12条)
法律が規則に必ず記載するよう求めている項目は以下の通りです。
|
必要的記載事項 |
内容・ポイント |
|
|---|---|---|
|
1 |
目的 |
どのような教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成するかという法人の根本的な活動目的。 |
|
2 |
名称 |
「宗教法人 ○○寺」といった法人の正式名称。 |
|
3 |
事務所の所在地 |
法人の主たる事務所(寺務所など)がどこにあるか。 |
|
4 |
包括する宗教団体の名称等 |
いわゆる本山や宗派など、上位の包括宗教団体がある場合にその名称を記載します。 |
|
5 |
役員の定め |
代表役員、責任役員等について、その資格、任免、任期、員数、職務権限などを定めます。法人ガバナンスの要です。 |
|
6 |
議決、諮問等の機関の定め |
責任役員会のほかに、檀信徒総会などを意思決定や諮問の機関として設置する場合に、その権限や運営方法を定めます。 |
|
7 |
事業に関する定め |
駐車場経営、幼稚園経営など、公益事業やその他の事業を行う場合に、その事業の種類や管理運営方法を定めます。 |
|
8 |
財産の設定、管理処分の定め |
基本財産や宝物を特定し、その維持・管理方法や、処分を行う際の手続き(責任役員会の決議など)を定めます。 |
|
9 |
会計等の定め |
予算、決算、会計に関するルール。特に会計年度(例:4月1日から翌年3月31日まで)は必ず定める必要があります。 |
|
10 |
規則の変更に関する定め |
この規則自体を変更するための手続きを定めます。慎重な手続きを定めることが一般的です。 |
|
11 |
解散及び残余財産帰属の定め |
法人が解散する場合の事由や、解散後の残余財産の帰属先を定めます。 |
|
12 |
公告の方法 |
法人が信者や社会に対して重要事項を知らせる(公告する)方法を定めます。「事務所の掲示場に掲示する」などが一般的です。 |
|
13 |
その他関連事項 |
上記各号に関連する事項を定めた場合に記載します。 |
3. 2019年法改正:役員の欠格事由の変更点
規則の必要的記載事項である「役員の定め」に関連して、非常に重要な法改正がありました。平成の終わりから令和にかけての法改正で、役員になれない者の条件(欠格事由)が変更されています。
- (旧)
改正前は、「成年被後見人又は被保佐人」は、その能力に関わらず一律に役員になれませんでした。 - (新)
令和元年9月14日施行の改正法により、この規定は削除され、新たに「心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」が欠格事由とされました(宗教法人法第22条)。
この変更は、単に戸籍上の身分で判断するのではなく、実際に役員の職務を遂行できるかどうかを個別的・実質的に判断することを法人に求めるものです。これにより、法人は役員を選任する際、候補者の能力をより慎重に評価する責任を負うことになりました。古い規則のままでは、この法改正に対応できていない可能性がありますので、確認が必要です。
4. 規則の作成・変更手続き|所轄庁の「認証」が必須
規則の変更手続きは法律で厳格に定められています。
- ステップ①:内部での意思決定
規則の「規則の変更に関する定め」の条項に従い、責任役員会での特別決議など、定められた手続きを正確に踏む必要があります。 - ステップ②:所轄庁への認証申請(宗教法人法第26条)
内部で変更案を議決したら、所轄庁に対し、「規則変更認証申請書」に関連書類(議事録の写し等)を添えて提出します。 - ステップ③:所轄庁による審査と認証
所轄庁は、手続きや内容が法令に適合しているかを審査します。必要に応じて、信者等への公告を命じられることもあります(同法第27条)。審査の結果、要件を満たしていれば変更が「認証」され、認証書が交付されます。 - ステップ④:法務局での変更登記
規則変更により登記事項に変更が生じた場合は、認証書到達から2週間以内に、法務局で変更登記を申請しなければなりません。
弁護士に相談するメリット
規則の作成・変更は、寺院の根幹に関わる重要な法務です。
- 現行規則の的確なリーガルチェック
- 実情に合った最適な規則案の作成支援
- 煩雑な認証手続きの代理
- 行政との円滑なコミュニケーション
まとめ
宗教法人の「規則」は、寺院の安定した運営と発展を支える、生きた“憲法”です。特に、役員の欠格事由に関する令和元年の法改正は、多くの法人で見直しが必要なポイントです。ご自身の寺院の規則が、最後にいつ見直されたか、現在の運営実態や最新の法令に合っているか、一度確認してみてはいかがでしょうか。将来のトラブルの種となる前に、ぜひ一度、寺院法務に詳しい弁護士にご相談ください。
長瀬総合のYouTubeチャンネルのご案内
法律に関する動画をYouTubeで配信中!
ご興味のある方は、ぜひご視聴・チャンネル登録をご検討ください。